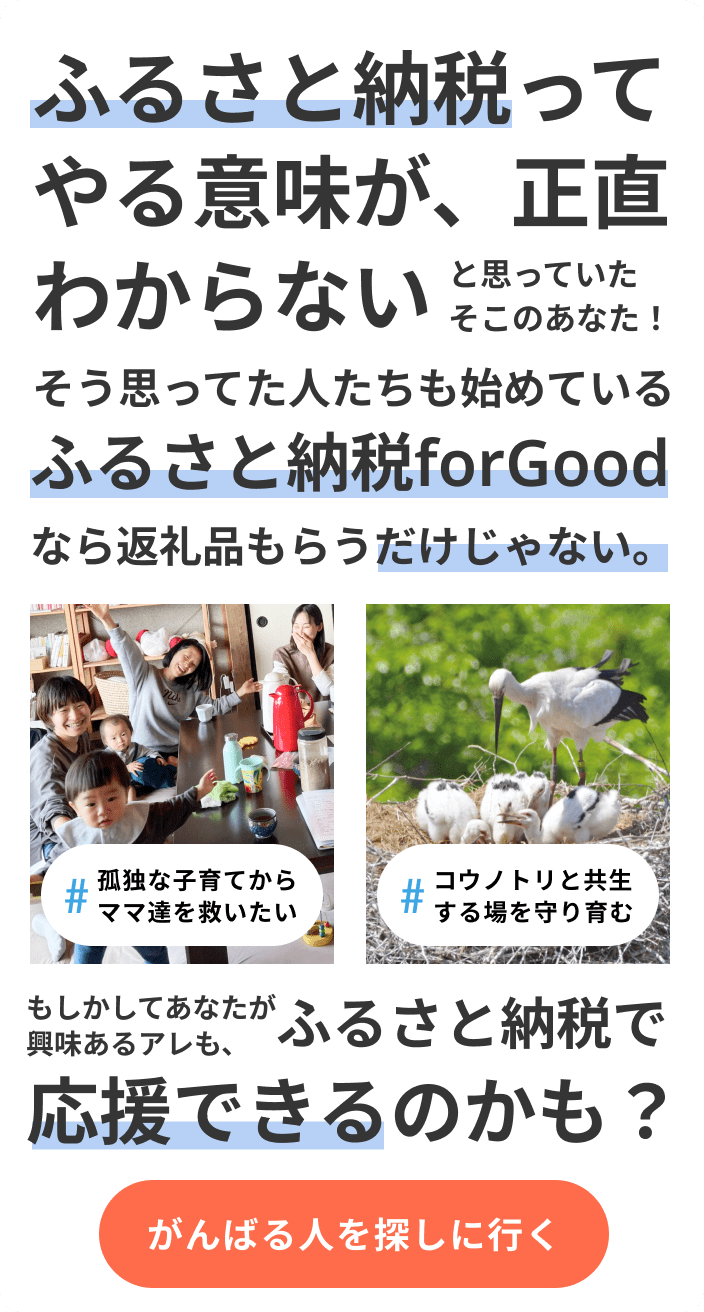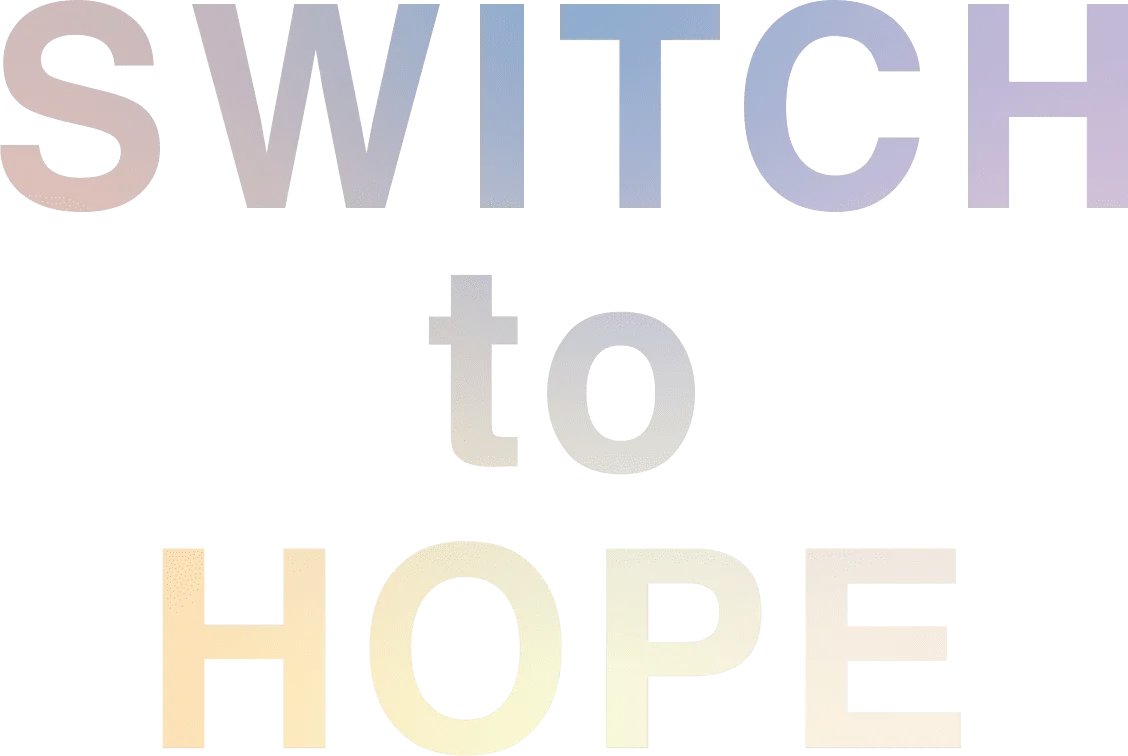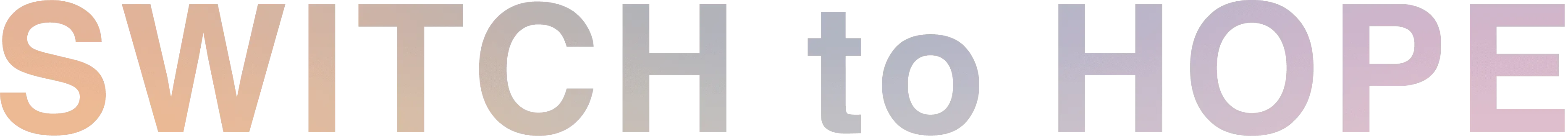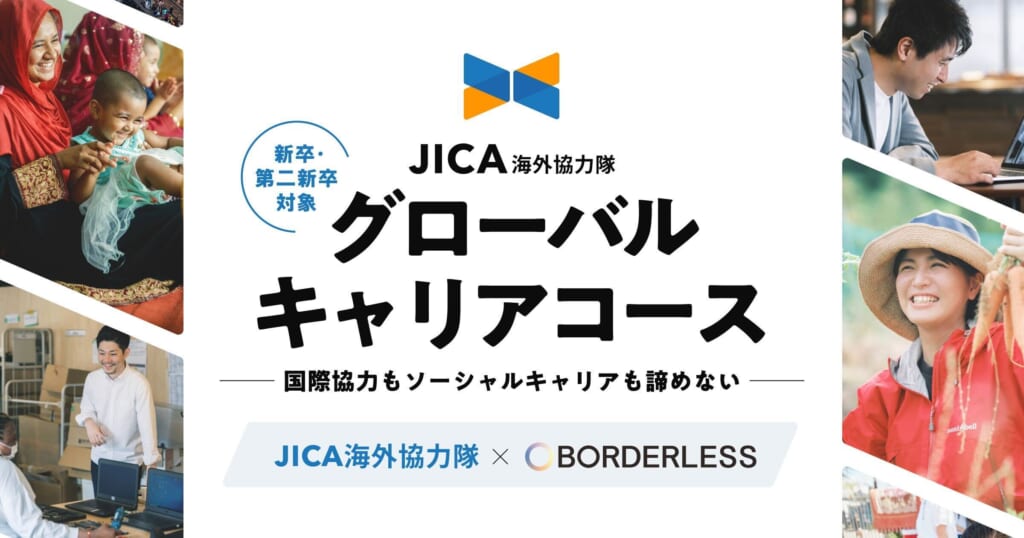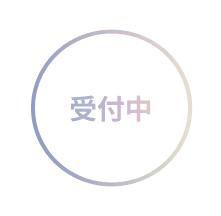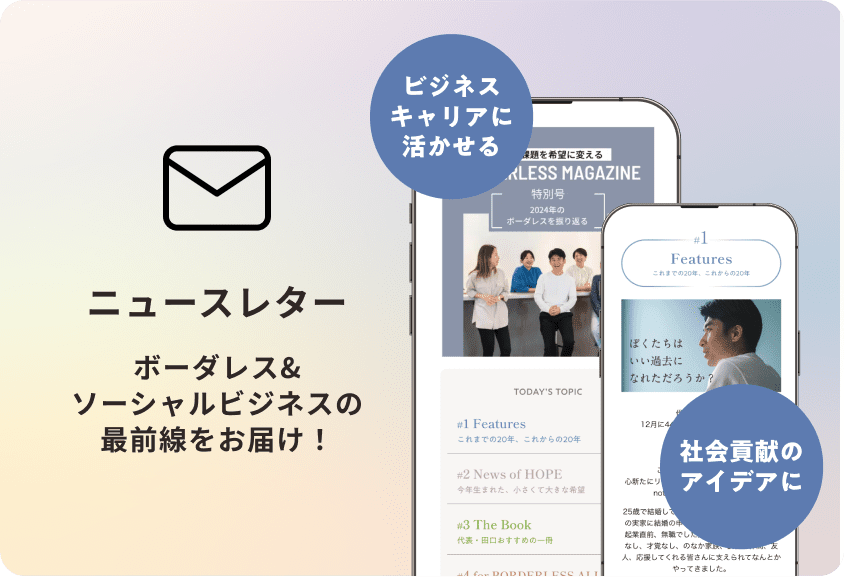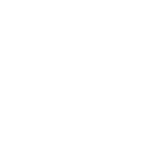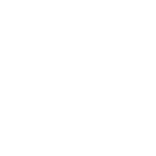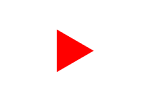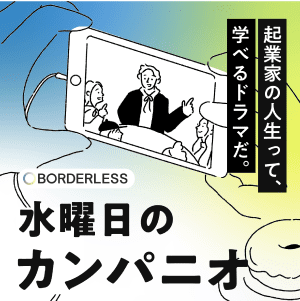社会起業家とは?社会問題をビジネスで解決する海外・日本の起業家一覧・事例
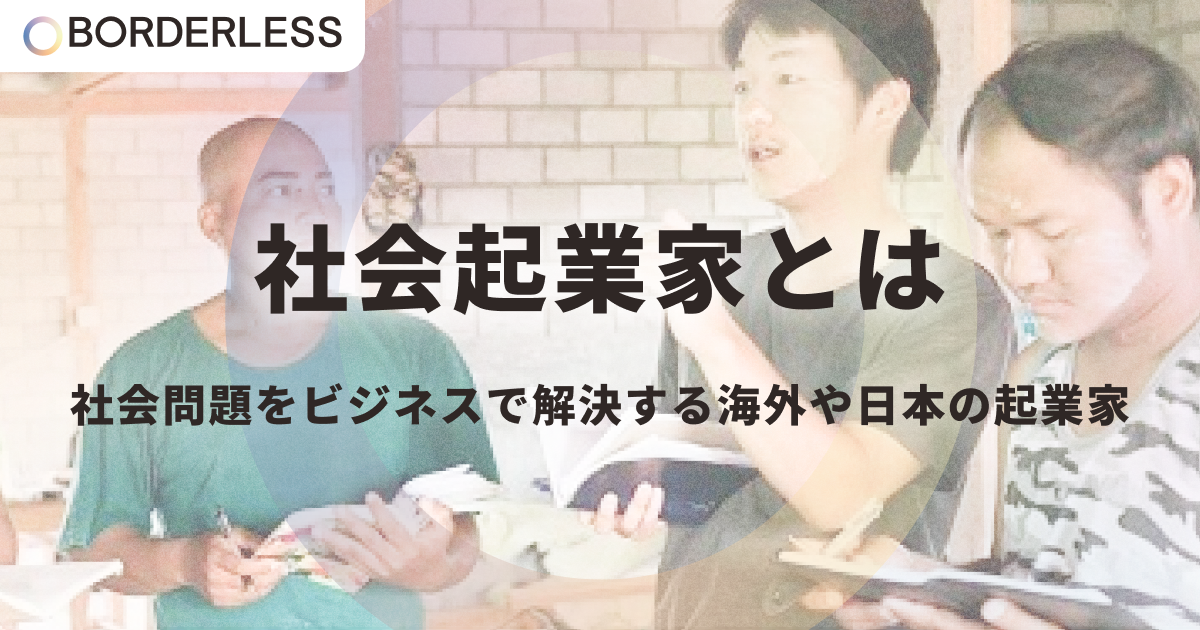
社会起業家とは、起業家の中でもビジネスを通して社会課題の解決に取り組む人のことを指します。そんな社会起業家が取り組むのは、貧困や差別、環境問題など、多岐にわたる社会問題。彼らは人生で目の当たりにしてきた社会問題を解決するために、NPOやボランティアという選択肢もある中で、起業という選択をとります。
今回は、社会起業家がなぜ社会問題の解決に「起業」を選択するのか、また世の中にどんな社会起業家がいるのかを解説&紹介します。
※本記事は2017年1月6日に『ボーダレス・ジャパン』のブログにて公開された記事を、再度内部のデータなどを調査、再編集し、2022年10月6日に更新したものです。
1. 社会起業家の定義
はじめに、社会起業家の定義について見ていきましょう。
例えばスタンフォード大学の起業家精神研究センターは、社会問題解決のために、伝統的なビジネススキルを用いて革新的なアプローチを考え出し、個人的よりむしろ社会的な価値を創造する人を社会起業家だと定義しています。
またアメリカ ミネソタ州の社会起業家研究所では社会起業家を、投資に対する経済的なリターンと社会的なリターンを同時に追い求め、社会的な目的を達成するために自ら事業で稼ぎ出す戦略をとる人だと定義。
日本国内では谷本寛治氏が、社会的な問題の解決にビジネスの力を活用して新しい仕組みを提示したり、新しいサービスを提供したりすることを通して社会的イノベーションを起こす人を社会起業家だと定義しています。
このように社会起業家の定義については、さまざまな人や組織がいろんな表現を用いて説明しているのです。しかしすべてに共通するのは、「社会問題をビジネスの力で解決する人」だということ。つまり社会起業家は、ビジネスの力で革新的で継続性を持った新たな社会的価値を生み出す人だと言えるでしょう。
2. 社会起業家と起業家の違い
ここまで社会起業家の定義について見てきました。その内容を見て「社会貢献をしている企業なら、世の中にたくさんあるのでは?」「あえて社会起業家と名乗る理由は?」と疑問に感じた人もいるのではないでしょうか。ここでは、社会起業家と起業家の違いについて解説します。
そもそも「社会起業家」というワードにも含まれている起業家とは、何もない状態から事業を立ち上げる人のこと。この中に、フランチャイズや事業継承などで事業を立ち上げる人は含まれていません。世の中のニーズを見つけ、そのニーズに応えるサービスなどを生み出す力に長けている人たちで、日本でも多くの起業家がイノベーションを巻き起こしてきました。
社会起業家もニーズに応えるサービスを生み出し、イノベーションを巻き起こす点では共通しています。ただし応えるべきニーズ、そして事業を興す目的が、すぐにでもサービスを生み出し広げなければならない「社会課題の解決」にあるのです。そんな社会起業家が立ち上げる事業が「ソーシャルビジネス」なのです。
ソーシャルビジネスについてはこちらの記事で解説しています。

社会問題解決を目的としたソーシャルビジネスでは、事業を立ち上げ自力で収益を上げ続けることで、貧困、差別、少子高齢化など国内外に数多く存在する社会問題解決に取り組みます。寄付などの外部資金にほとんど依存しないため、スピーディーかつ継続的な社会問題の解決が期待できるのです。
起業家が事業を立ち上げ進めた結果、社会の役に立つことは往々にあるでしょう。ただ社会起業家の場合は、彼らがこれまでの人生で目の当たりにしてきた社会問題を解決するために事業を立ち上げます。
つまり社会起業家と起業家には社会問題をなくし、よりよい社会をつくっていくための事業を立ち上げるという「事業の目的」の部分で違いがあるのです。
3.世界や日本の社会起業家たち
近年、社会問題を解決する手段にソーシャルビジネスを選択する社会起業家が増えてきています。ソーシャルビジネスについて解説した記事でもその規模感について触れていますが、イギリスでは2012年以降、約5万8千だった社会問題解決に取り組む企業の数が約74万まで増加し、日本でも2008年時点で約8,000社だった企業数が約20万5千社まで増えているというデータが出ているほど。
では実際にどのような社会起業家が活躍を広げてきたのか、ご紹介します。
3.1世界の社会起業家
ムハマド・ユヌス(バングラデシュ/グラミン銀行)
バングラデシュの実業家で、グラミン銀行総裁である、ムハマド・ユヌス。彼は大学で教鞭をとっていた頃に、村人が金貸し業者から借金をすることで貧困サイクルから抜け出せなくなっている状況に気づき、彼らの自立を支援するため小口金融業を始めた。これがグラミン銀行設立のきっかけとなる。グラミン銀行は、1日1ドル〜2ドルで暮らしている最貧困層の人たちに対し、自立を目的として数ドル程度の少額の融資を行うという小口金融。このモデルは「マイクロファイナンス」、「マイクロクレジット」と呼ばれ、現在では世界中に広まっている。2006年に、ノーベル平和賞を受賞。
イヴォン・シュイナード(アメリカ合衆国/パタゴニア)
アウトドアの衣料品ブランドパタゴニアの創始者である、イヴォン・シュイナード。クライミングを始めたことをきっかけに、道具を自前で製作し販売するようになり、多くのクライマーから支持されるように。しかしその道具が岩肌を傷ついていることを知った彼は、環境問題に取り組むようになった。環境責任を果たすことは、今でもパタゴニアの根幹をなす理念として据えられており、現在もすべてのコットン商品をオーガニックコットンで製作したり、売上の一部を環境保全団体に寄付したりするなどして、積極的に環境保全に取り組んでいる。
アニータ・ロディック(イギリス/ザ・ボディショップ)
ザ・ボディショップの創業者である、アニータ・ロディック。彼女は世界中を旅して出会ったさまざまな自然の原料を化粧品にして、量り売りすることを思いつく。そしてその製造過程でよく行われる動物実験は一切行わず、パッケージにおいても再生素材を利用するなど、環境・動物に配慮したサプライチェーンを徹底し、従来の化粧品製造のあり方に一石を投じた。また彼女は、売り上げの一部を環境保護団体や人権擁護団体に寄付したり、啓発イベントを開催したりして、環境や動物に配慮する活動に積極的だった。
3.2 日本の社会起業家
犬井智明(BODERLESS LINK、Borderless Myanmar Fertilizer)
学生時代にミャンマーの難民キャンプに参加したことをきっかけに、ソーシャルビジネスの道を志し、株式会社 ボーダレス・ジャパンに入社。24歳でミャンマーに渡り、倒産寸前だった事業をV字回復させ、その後新規事業も開発。
辺境地の小規模農家に適正価格での資材販売や技術指導、マイクロファイナンスを提供し収入の向上を図る農業サービス ボーダレスリンクは、利用者数1万5000人、今期の売上は15億円を見込む。また、有機肥料を製造し販売するBorderless Myanmar Fertilizerは、農村部の仕事のない人々に150名ほどの雇用を生み出す。また、社会起業家を生み出す ボーダレスミャンマーの代表も務め、ミャンマーの社会問題解決を推進している。
Borderless Myanmar Fertilizerについて詳しく知る
薬師川智子(Alphajiri Limited)
青年海外協力隊員としてケニアへ赴任し、現地の人々とともに暮らす中で、異なる価値観を持つ人々とのぶつかり合いに刺激を受ける。農村の生き方にひとの幸福のあり方を見出した一方、貧困という問題にも直面し、自分が人生で貢献すべき課題の一つだと感じアルファジリを起業する。2017年、ボーダレスグループにジョイン。農産物サプライチェーンに関わる様々なビジネスモデルで挑戦しながら、現在は貧困農村からの農産物買取と加工、卸売と小売店舗経営を通して、貧困問題解決に取り組む。
中村将人(Sunday Morning Factory)
株式会社ボーダレス・ジャパンに新卒入社し、既存事業で1年間マーケティングを学んだのち、バングラデシュの貧困地域における児童労働問題の解決のため、新規事業を立ち上げるも2億円の赤字に。その経験を活かし、2017年オーガニックコットンのベビー服ブランド「Haruulala organic」を立ち上げ独立。ベビー服は日本中の百貨店や産院で導入され、現在バングラデシュの自社工場で150名の仲間と共に、さらなる雇用の創出と、子どもたちの人生が生まれた環境で決まらない社会作りに取り組む。
伊藤綾(きら星)
学生時代よりまちづくりに興味があり、不動産による開発で持続的な地域づくりをしてみたいと転職。地方の人口減少による商業環境への影響といった大手資本主導での打ち手に限界を感じ、民間から地方の衰退に取り組めないかと移住促進を主なアプローチとしたきら星株式会社を越後湯沢に創業。
自治体連携、地方のまちづくり会社との連携を基盤に「住みたい街を次世代につないでいく」をビジョンに、職業紹介・スペース運営・起業支援等を行う起業家。Forbes Japan「世界を救う希望 NEXT100」に選出。
菊池モアナ(Borderless Tanzania Limited)
大学時にアフリカ・タンザニアにて「子供が退学する理由」の調査を行い、約3人に1人が10代で妊娠し退学をせざるを得ない女の子たちの現状を目の当たりにする。その後、自身も予期せぬ妊娠をし大学生でシングルマザーになる。
株式会社ボーダレス・ジャパンに新卒起業家として入社し、2年目には若年妊娠で退学したシングルマザーが働ける場としてBorderless Tanzania Limitedを設立。生理用ナプキンの製造・販売および寄付と性教育の無償提供を行う事業LUNA sanitary productsで雇用を創出し、同時に「生理の貧困」の解決を目指す。
LUNA sanitary productsについて詳しく知る
原口瑛子(ボーダレス・ブルキナファソ)
学生時代に「ハゲワシと少女」を見て、貧困をなくすという志を持つ。2010年JICAに入構、中南米の円借款等を担当。2015年ボーダレス・ジャパンに入社、2017年ビジネスレザーファクトリー代表に。バングラデシュでは700人の職人を迎え、日本では150人の仲間と18店舗(当時)を展開。2022年に代表を退任し、同年ブルキナファソに渡り、ボーダレス・ブルキナファソ設立。テロの影響を受けた女性の雇用創出し、コミュニティをつくることで経済的安定と精神的安定を実現。女性たちや子どもたちの希望を創り、その先にある平和な社会の実現を目指す。
池田将太(ハチドリソーラー)
小学校から高校までプロ野球選手を目指して野球に打ち込む毎日を過ごしていたが、大学入学後、国際協力を志すようになりミクロネシア連邦で環境活動に従事。新卒でボーダレスジャパンに入社。その後、自然エネルギーが主電源の未来を創るをミッションにハチドリソーラー株式会社を設立。現在はアフリカの難民問題を解決する新規事業の立ち上げにも取り組む。
三原菜央(スマイルバトン)
新卒から8年間専門学校の教師として働く中で、生徒から「一般企業に就職したい」と相談され社会について何も知らない自分に気付いたことをきっかけに会社員へ転職。キャリアを積む中で、少しかけ離れたところにある学校と社会の間に橋を架けたいと考え、両者が一緒に学べる場「先生の学校」をライフワークとして活動を開始。2020年に株式会社スマイルバトンを立ち上げ、教育メディアコミュニティを通して、先生と子ども両者にとって、学校が行きたい場所になり、人生を豊かにすることを目指している。
相原恭平(むすびば)
学生時代にスリランカでの国際ボランティアを通して海外貧困層の現状を知り、1年間休学してベトナムとインドでボランティア活動をする。ベトナムでの出会いから、技能実習制度にかかわる課題を解決すると心に決め、2020年ボーダレス・ジャパンに新卒で入社。2021年5月に日本語教育を通して技能実習生の失踪問題を解決するため、むすびば株式会社を創業。技能実習生向けの日本語教育の機会を提供し、実習生が「日本に来てよかった」と思える社会を実現を目指している。
4. 社会起業家に求められること
社会起業家は前述のとおり、社会問題を解決するために事業を立ち上げます。つまり社会問題を解決しなければその事業が成功したとは言えません。
そのため、第一に必要とされるのは、「志」。

例えば、海外の貧困農家に安定した収入をもたらすビジネスの仕組みをつくるとします。貧困農家の人々は高度な農業技術を持っておらず、彼らが所有する土地は痩せていて、水も十分にありません。
このような状況に対してビジネスでの解決を図るわけですが、土地の育て方や上下水設備などの現地ならではの独自ルールに悩まされることが想定されます。またそもそも、そこでそのビジネスを展開する理由を理解してもらうのに時間がかかることも考えられるでしょう。
このようにソーシャルビジネスは、事業を立ち上げる前だけでなく立ち上げたその先にも問題が山積されているため、「何がなんでも、目の前にある社会問題を解決する」という強い想いが重要です。
5. 1人でも多くの社会起業家の誕生が、より多くの社会問題を解決する
数えきれないほどたくさんある、社会問題。しかもそのどれもが多様かつ複雑になっているため、解決に時間がかかっています。そんな社会問題を自分の力でなんとか解決したいと、日本や世界で多くの社会起業家が動き出しているのです。この事実は、多くの人がありとあらゆる社会問題に関心を持ち、よりよい社会をつくりだしたいと思っていることの証だと思います。

もしもあなたの心の中に、解決したい社会問題があるのなら、社会起業家として動き出すのも1つの手ではないでしょうか。もちろん社会問題を事業を成り立たせた上で解決に導くのは、とても困難な道のりになるでしょう。しかし「自分がこの社会問題を解決して、よりよい社会をつくる」という熱い志があれば、あなたはすでに社会起業家としてのスタートラインに立っています。事業を進める中で、あなたの志に共感する人も出てくるでしょう。
社会起業家が実行するソーシャルビジネスは、迅速な社会問題解決の突破口となりえる手法です。1人でも多くの社会起業家が活躍するようになれば、世界はより良くなっていくと思います。
社会問題を解決するための第一歩を踏み出しませんか?
ボーダレス・カンパニオでは、様々な社会問題の解決に向けた「第一歩」になるようなステップを準備しています。
人や環境に配慮したサステイナブルなものを暮らしに取り入れる「個人向けサービス」
ソーシャルビジネスを深く知る 書籍「9割の社会問題はビジネスで解決できる」
社会起業家をみんなで応援する仕組み「アライになる」
ぜひご自分にあったステップを見つけて、第一歩を踏み出してみてください。
社会問題をビジネスで解決する仲間を募集しています
ボーダレス・カンパニオでは、社会問題をビジネスで解決したい人を募集しています。難民の問題や貧困、差別偏見、環境問題など、あなたが解決したい問題を解決する事業をビジネスで解決していきませんか?
ソーシャルビジネスで社会問題を解決し、社会変革を起こそうとする仲間を待っています。
社会起業家としてソーシャルビジネスを立ち上げたい方「社会起業家募集」
自分のプロフェッショナル領域を活かして社会問題に取り組みたい方「採用情報」
ソーシャルビジネスで社会問題に取り組みたい新卒の方「新卒で新規事業立ち上げ」
ソーシャルビジネスの作り方、社会起業のイロハが学べる実践型アカデミー「ボーダレスアカデミー」
執筆 / クリス
福岡在住のフリーライター。ボーダレス・ジャパンを4ヶ月で退職し、いまはパートナーとしてインタビューや執筆を手掛ける。愛猫“雛”をおなかに乗せソファに寝っ転がってアニメを見たりマンガを読んだりする時間が至福。仕事よりもこちらに時間を割きすぎる傾向があるが、やるべきことはやる。企業の採用コンテンツやブライダル、エンタメなどのメディアでも執筆。
【参考】
・社会起業家の研究―変革をもたらす行動モデル―(2002.12) 高知工科大学大学院 工学研究科基盤工学専攻 起業家コース 山本 千香子
・中京経営紀要 第7号 「社会起業家と従来型起業家」(2007.2) 速水 智子/中京大学大学院経営学研究科