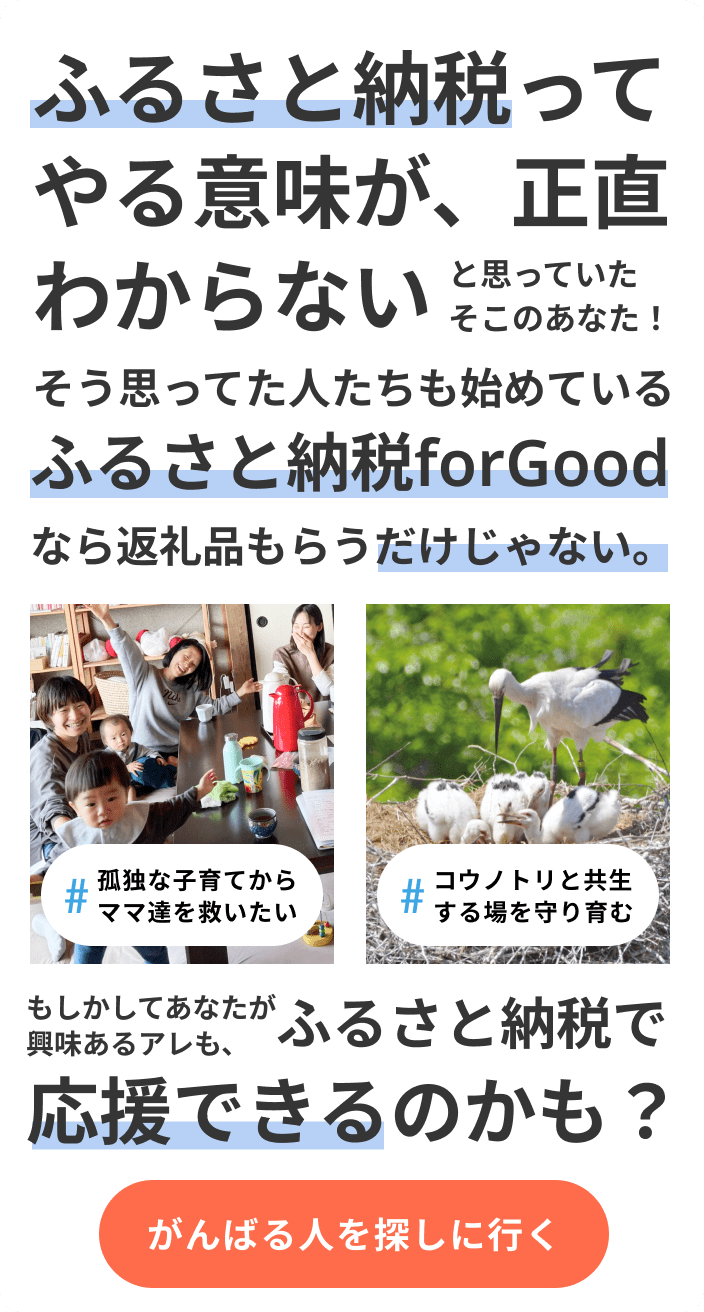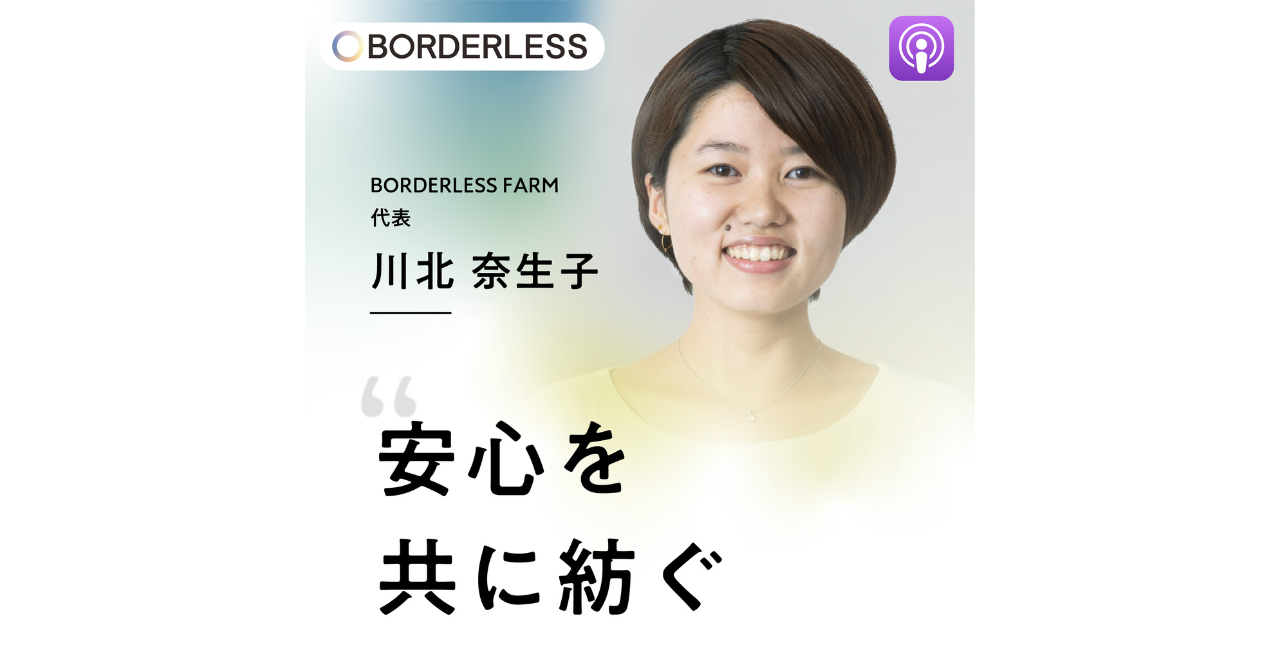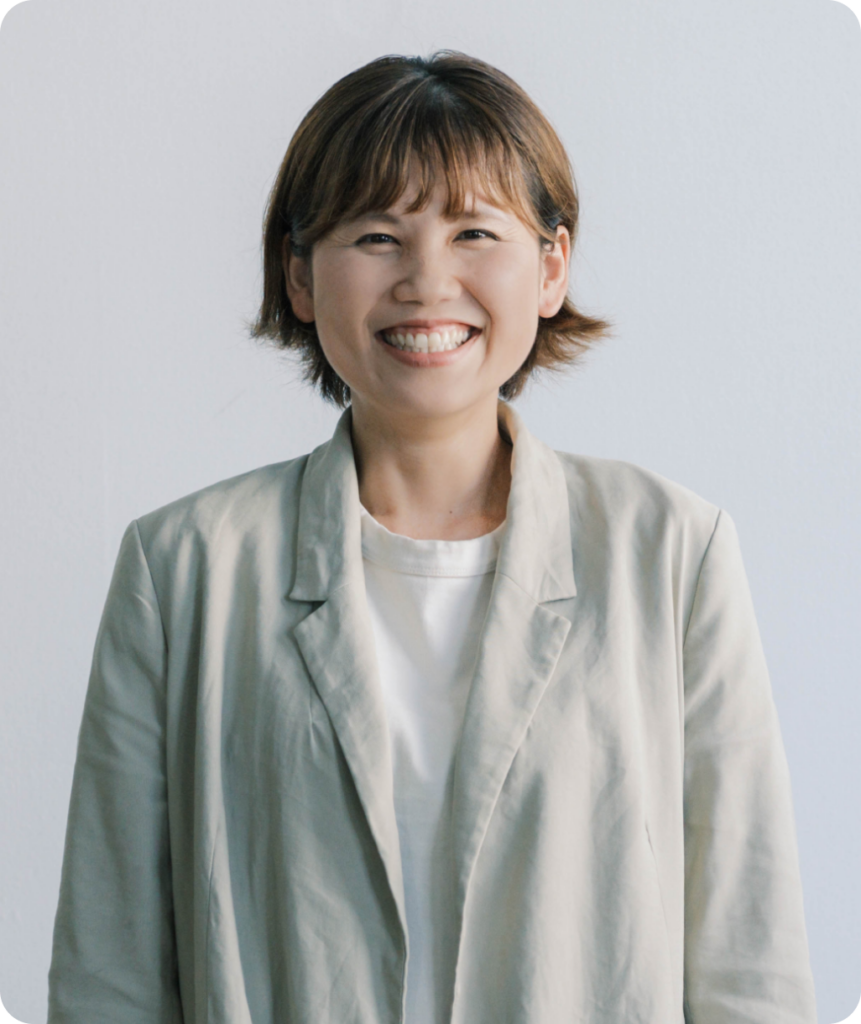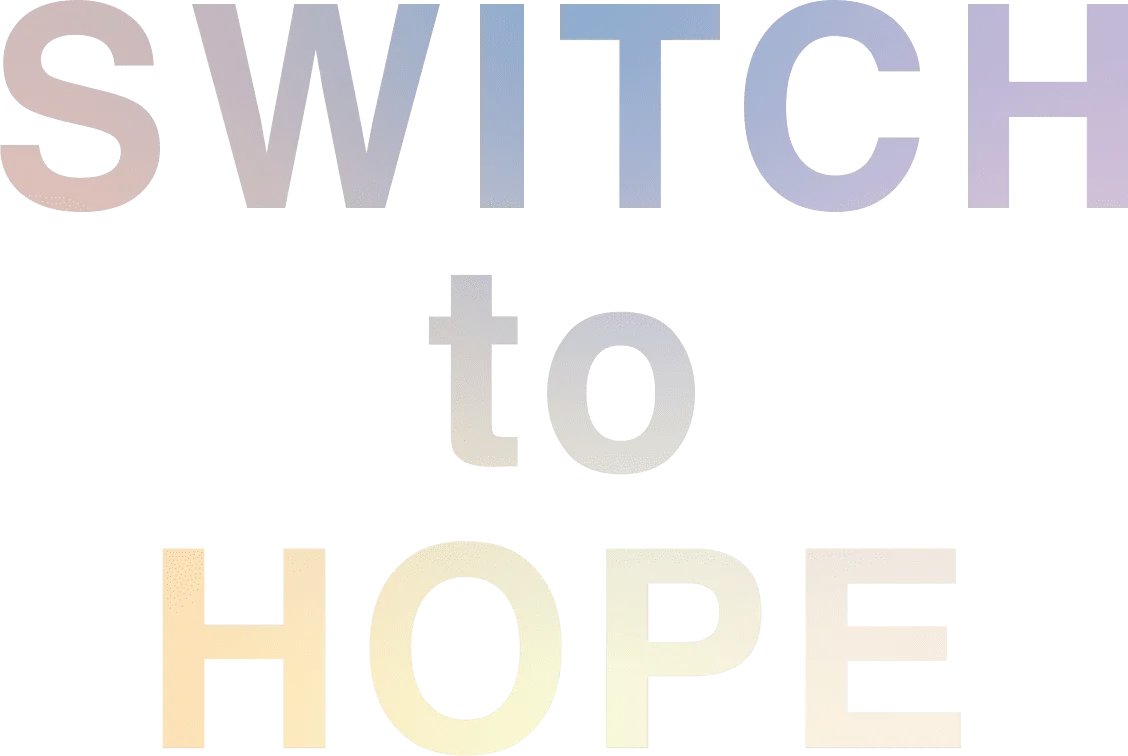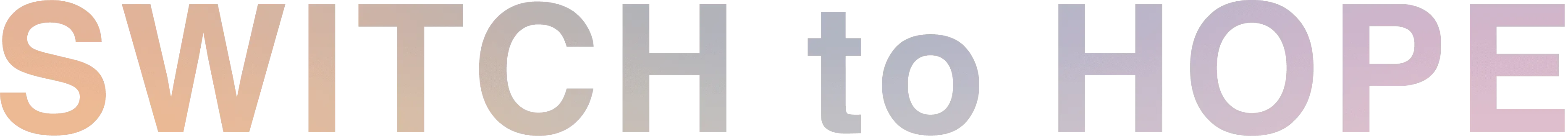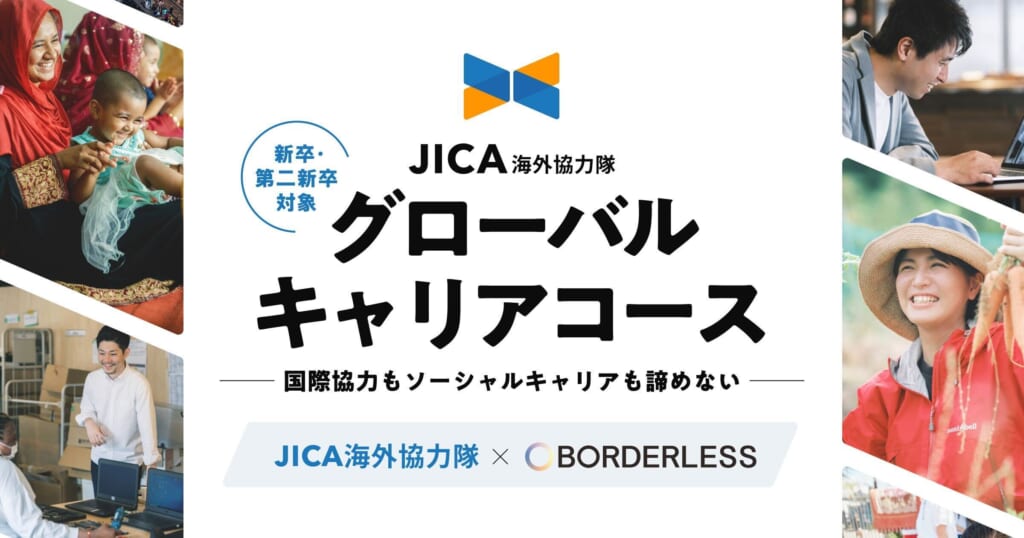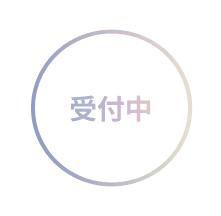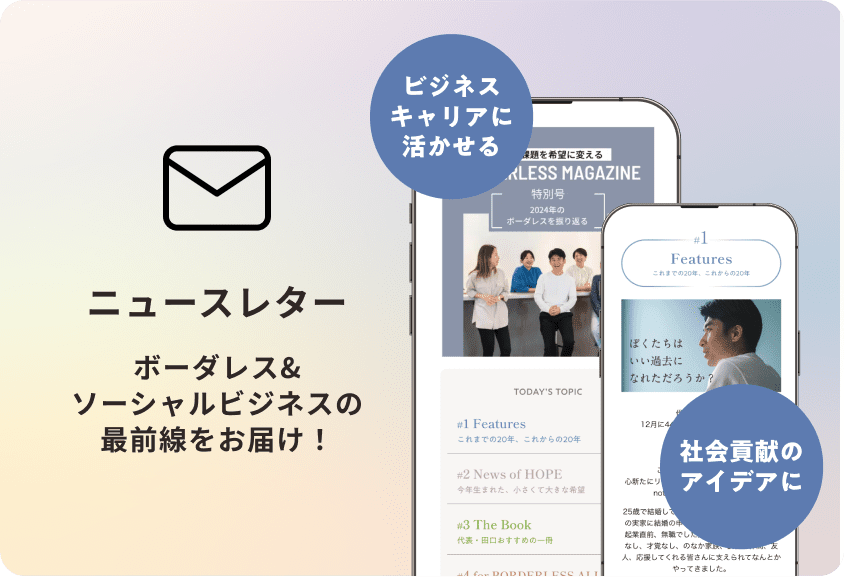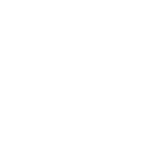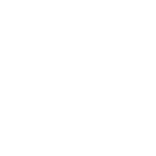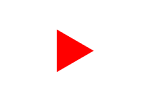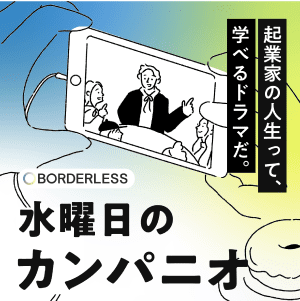BORDERLESS FARM 代表取締役 川北 奈生子

まわりの大切な人たちと手を取り合い、支えあって生きていける社会をつくりたいです。
生活を安定させ、将来の不安を減らすことで、未来に向かって前向きに進むための第一歩を支えられたらと思っています。
HISTORY
これまでの歩み
-
22才
フィリピンNGOにてインターン
大学在学時から継続し、フェアトレードココナツオイルの商品開発、販売に従事
-
23才
ボーダレス・ジャパン入社
ビジネスで社会問題を解決できる力をつけるため、マーケティングを学ぶために入社
-
24才
ミャンマーにてハーブ加工工場責任者就任
日本基準の衛生管理を導入し、製造ラインを整え、日本への輸出を実現
-
26才
ミャンマー法人BORDERLESS FARM Co., Ltd. 代表取締役就任
栽培品目をハーブから野菜に拡大し、契約栽培を事業の軸に据える
-
27才
株式会社BORDERLESS FARM創設・代表取締役就任
生産増に応じての販路拡大のため、日本にてハーブティーOEM事業開始
01
どうしてボーダレスに?

高校生のとき、パキスタンで学校を建てるアメリカ人の方の本を読み、宗教や文化の違いがあっても、お互いを思いやって生きている彼らの姿にあこがれました。同じように自分も働きたいと思い、大学時代はフィリピン、入社後はミャンマーにて活動する中で、優しく、あたたかい人々と出会い、彼らの幸せを心から願うようになります。
一方で、貧困状態にある人々の暮らしは厳しく、頑張っても報われづらい社会構造を目の当たりにしてきました。ゴミ山から食べられるものを探して生きている子どもたち。借金返済のために、バラバラで暮らす家族。麻薬や死のリスクがずっと身近にある暮らし。
たまたま日本で恵まれた家庭に育った自分との差に愕然とし、彼らが直面するリスクを少しでも減らし、安心して暮らせる社会をつくれればと思い、起業を決意しました。 文化や感覚の差が大きい、ミャンマーの農家さんはじめとした生産者の人々と、卸先の企業さんたち。多くの企業が双方への理解が足りず、事業撤退してきました。
私たちはその間にたち、対等なパートナーとしてつきあっていけるよう、栽培方法を伝え、品質をととのえ、信頼関係を築いていきます。
02
今の仕事の喜びは?
農家さんの生活が安定し、喜んでくれている姿をみるのはもちろん嬉しい瞬間です。
「子どもたちを大学まで行かせてやりたいから、頑張って貯金している」という農家さんの声。借金に追われ、その日の食事を心配していた彼らから、明るい未来を語る声を聞くと、この事業を続けてよかったと心から思います。
でも、それだけではなく、農家さんとお客さんである農産物卸先の企業さんから、商品の品質にご満足いただけたときには、とても誇らしい気持ちになります。
ひとつひとつの作物に、手をかけ、心をこめて育ててくれている農家さん、それをより良い形でお客様にお届けしようとしてくれるメンバーの頑張りが評価されたように感じられるからです。
農家さんやメンバーは、輸出し、お客さんに喜んでいただける作物を育てることに、プライドをもって仕事をしてくれています。「こんなにきれいなハーブ・野菜はどこにもない」と胸をはっている彼らの笑顔こそが、私たちの事業の宝だと思っています。

03
次のチャレンジは?
2021年にミャンマーでクーデターが発生してから、国内の状況は一変してしまいました。
銃撃戦が発生し、避難を繰り返しながら暮らしている農家さんたち。多くの企業が撤退し、とんでもないルールがまかり通る今のミャンマーでの事業を続けていくことに、心が折れそうになることもあります。
でも、そんな状況だからこそ、私たちのように、地道に信頼関係を築き、農家さんの生活を足元から支えていく事業が必要とされていると思います。どんなに難しい状況でも、ミャンマーで生きていく人々には日々の暮らしがあるからです。 少しでも安定した暮らしを、一人でも多くの農家さんに届けるため、事業の海外展開と作物の多角化を目指しています。
生産者と卸先を直接つなぎ、信頼関係を築いていく契約栽培。卸先が増えれば増えるほど、事業は安定し、より多くの農家さんをパートナーに迎え入れることができるようになります。先行きが不透明なミャンマーだからこそ、揺るがない強い絆を築いて、農家さんの生活を支えていきたいです。

わたしが働く会社
OTHER FELLOWS
他のフェロー
NEWS
for HOPE
様々な人たちと、社会に
HOPEを作り出していきます
EVENT
for HOPE
イベント開催情報や社会問題理解を
深める機会をお届けします。

ボーダレスで働く人、社会起業家についてわかるPODCASTを放送中

採用説明会やイベント、インターン
情報をいち早くお届けします!