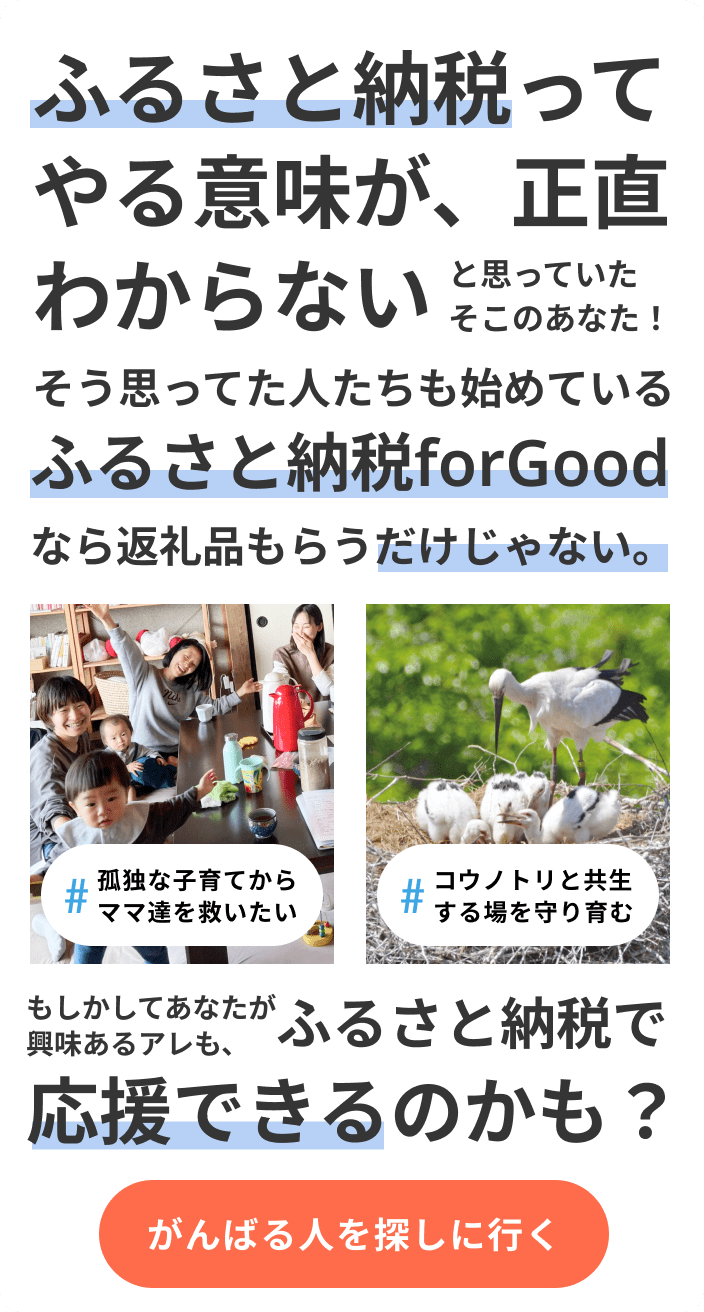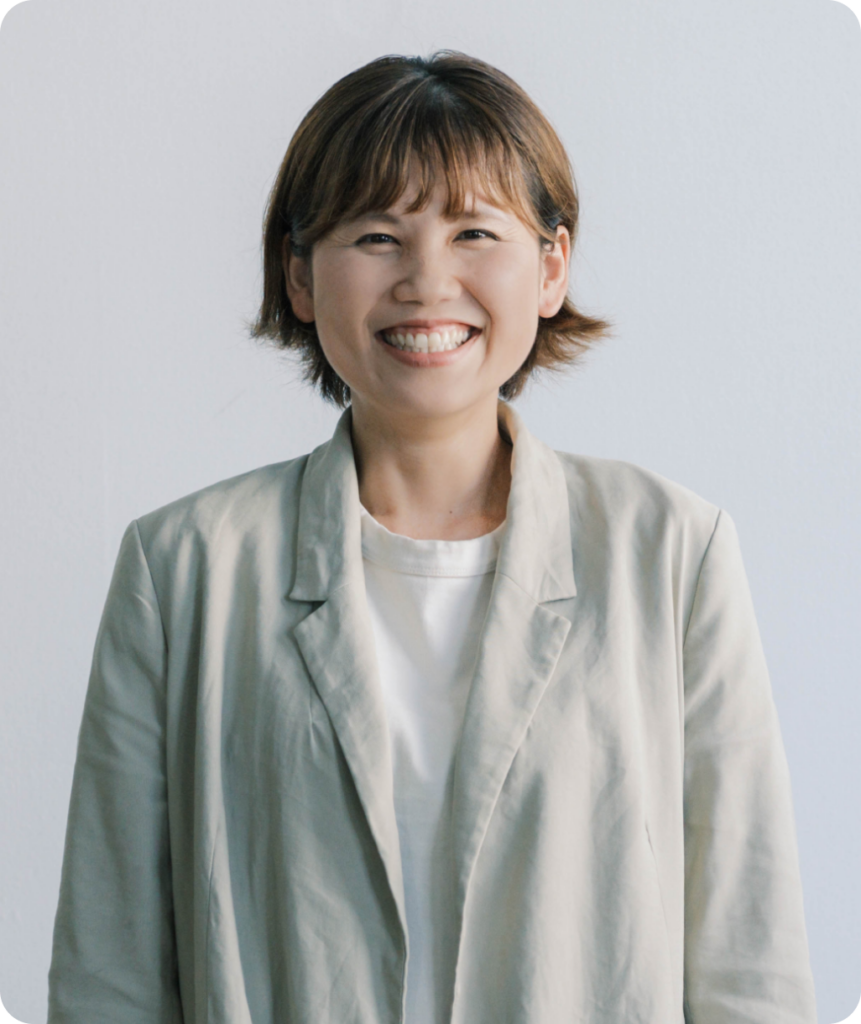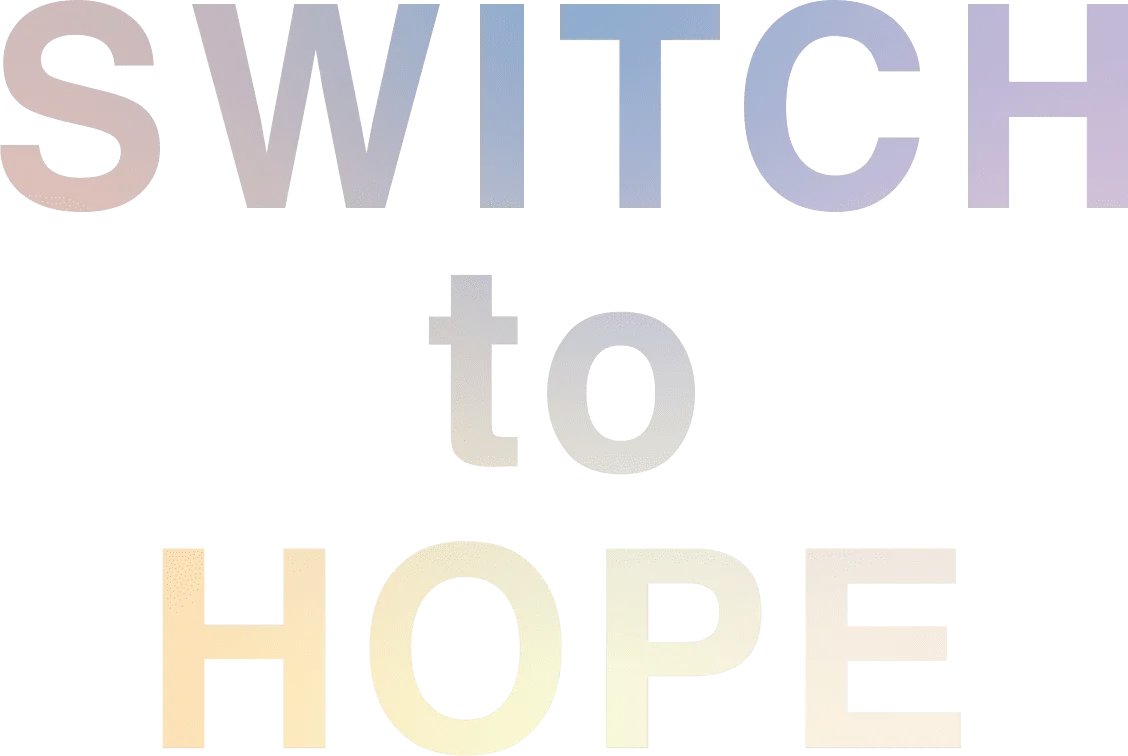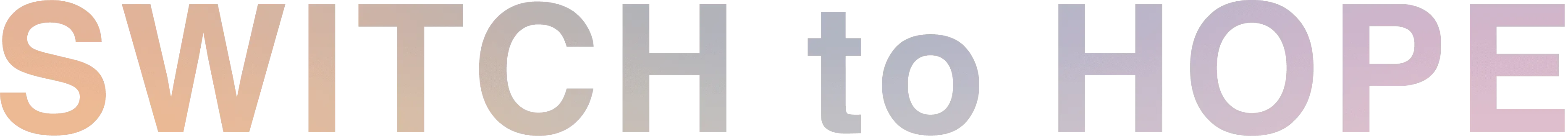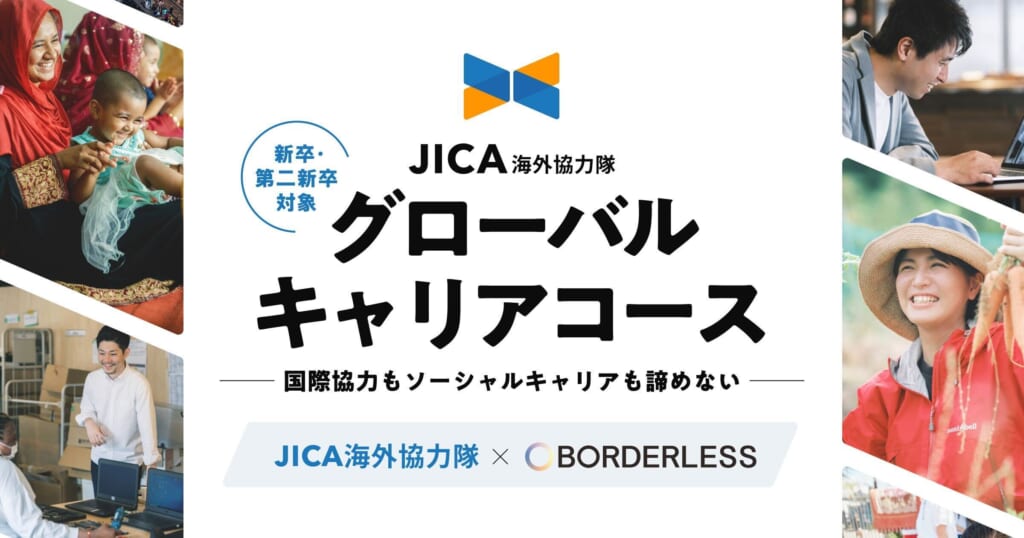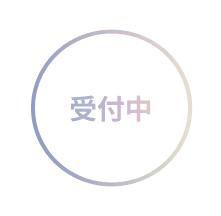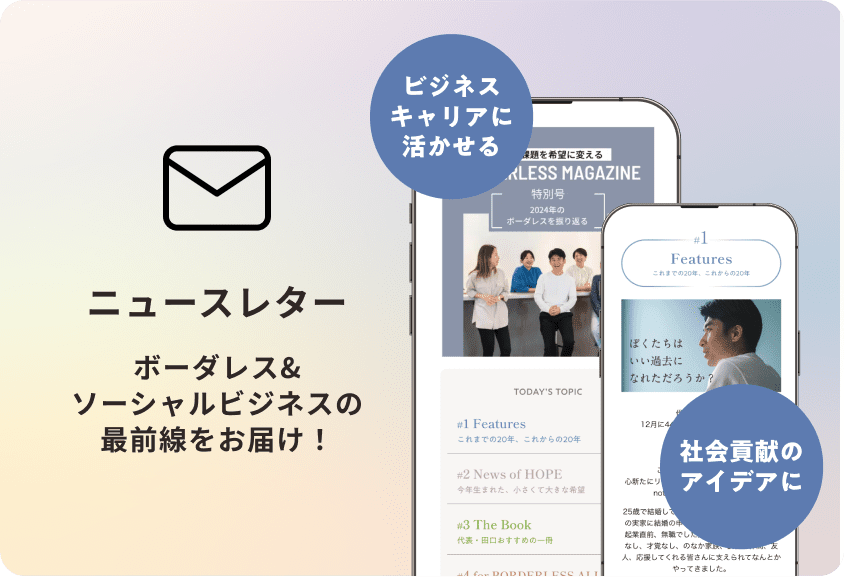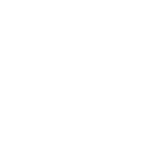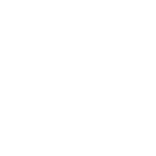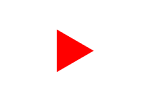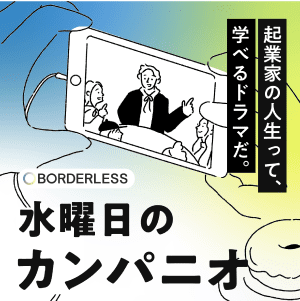Relight 代表 市川 加奈

一度社会的な信用を失った人に厳しい日本。そんな現状を、生活を立て直すためのちょっとお節介な事業をつくることで、自分の将来に夢や希望を抱き、明日が待ち遠しくなるように変えていきます。
HISTORY
これまでの歩み
-
22才
JOGGOにて海外工場での生産から顧客対応までを統括
新卒入社で革製品事業のJOGGO配属になり、生産から顧客対応を通して事業のつくり方を学ぶ。
-
24才
新規事業の国内工場を工場長として立ち上げ
JOGGOの新規事業(現UNROOF)として、精神・発達障害者が働く国内工場を立ち上げる。
-
26才
ホームレス問題がテーマのRelight株式会社を起業
01
なぜ会社を立ち上げたのか?

東京の山奥で育ったので、少し都会の高校に行くようになって初めて、路上で生活している高齢の方を見かけました。 当時、介護福祉士を目指していたこともあり、寒空の下で段ボールを敷いて震えながら編み物をしている方の存在が気になり始めます。 しかし何もできない自分と、周りの見て見ぬふりの大人にモヤモヤしたのことが、ホームレス問題に取り組もうと決めた最初のきっかけです。
その後大学に進学し、国内外の貧困問題を学ぶようになります。 全国の炊き出しや夜回りに参加させてもらい、支援者や当事者とお話をする中で、支援ではなくビジネスという手法で社会の仕組みを変えることができないか考えるようになります。
一般企業に就職よりも、今までやってきたこと、かつ自分のやりたいことを早くかたちにしたいと思い、ボーダレス・ジャパンに新卒で入社しました。
約3年、JOGGOにて生産管理や、精神疾患・発達障害のある方が働く国内工場の立ち上げを行い、事業を通じてソーシャルビジネスのつくり方を学びました。 そしてJOGGOを卒業後に現在の会社を立ち上げ、日々ホームレス問題をはじめとする日本の貧困問題に向き合っています。

02
今の仕事の喜びは?
相談に来られた方の感謝の言葉も嬉しいですが、気を遣って言わせてしまっている可能性もあるので、どちらかというと、紹介した企業の方から「あの人、頑張ってるよ」「楽しそうに働いているよ」とお話を聞いたりするほうが嬉しくて。 私たちの考えた仕組みが、誰かの人生をちょっと良い方向に進めるきっかけになったときにやりがいを感じます。
具体例をいうと、北海道から身一つで来社された男性は、最初、「家族も仕事もしんどくなってしまって、家を飛び出してきた。いま手元に10万円あるので、これが尽きたら死のうと思う」と話していました。 いろいろお話を聞く中で、調理の仕事を今までしていたということがわかり、その後高齢者施設で調理の仕事を紹介しました。
数か月後、久しぶりにその方とお会いすると、顔つきが全然違ったんです。 顔が強張っていなくて、目にも光が差し込んでいて。 生活が少しずつ安定してきていることを語らずともわかる瞬間でした。
「将来は自分で飲食店をやりたい」と話してくれたその方のように、自分の将来に夢や希望を抱けるようなきっかけをこれからもつくっていけたらと思います。

03
次のチャレンジは?
現在は「仕事」に関しての事業が中心ですが、一つの事業だけではどうしてもそれに当てはまらない方が出てしまいます。 寮付きの仕事の紹介では、働けない方や仕事はしているが家のない方には対応できないこともありました。
特にホームレス問題は、その背景も解決策も複雑なので、路上生活や現在家のない方に絞らず、多方向から解決に向けてアプローチできる事業をつくって対応していこうと考えています。
具体的には、仕事はしているが身寄りがいない方や、過去の滞納歴から審査が通らず、自分で部屋を借りられない方向けに物件を提供すること。 また、適切なタイミングで適切な情報に繋がれず困窮してしまう方のために情報を届けるメディアの運営を考えています。
一度社会的な信用を失った人が自力で立て直すのは難しいので、もう一度頑張ってみようかなと思えるような、何度でもやり直せる社会の仕組みをつくっていきます。

MEDIA / AWARD
メディア出演・受賞歴
-
TV
BSテレ東
(2024.03.23)テレビ東京
(2022.07.16)BSテレ東「一柳良雄が問う 日本の未来」
(2022.06.11)ABEMAヒルズ
(2022.01.21)フジテレビ/めざまし8
(2022.03.03)テレビ東京
(2021.10.22)BSテレ東「日経ニュース プラス9」
(2021.04.15)BS朝日「Fresh Faces -アタラシイヒト-」
(2020.12.12) -
BOOKS
フォレスト出版「大人も子どもも知らない不都合な数字」
(2024.03.09)小峰書店「仕事ファイル」
(2023.04) -
WEB MEDIA
東京新聞
(2023.01.01)bizSPA!フレッシュ
(2022.04.08)朝日新聞DIALOG
(2022.02.09)eltha(エルザ)
(2022.02.02)朝日新聞デジタル
(2022.01.06)taliki.org
(2020.8.27)日刊SPA!
(2020.7.11) -
RADIO
TBSラジオ
(2022.04.07) -
MAGAZINE
月刊経団連11月号
(2022.11)ニューズウィーク日本版 特別編集「未来をつくるSDGs 2022」
(2022.02) -
AWARD
Forbes主催『Forbes 30 Under 30 Asia 2022』選出
(2022.05)Forbes JAPAN主催『30 UNDER 30 JAPAN-日本発「世界を変える30歳未満」30人-』選出
(2021.10) -
SEMINAR
ICCサミットKYOTO 2022「ソーシャルグッド・カタパルト – 社会課題の解決に挑戦-」
(2022年9月5~8日開催)
わたしが働く会社
OTHER FELLOWS
他のフェロー
NEWS
for HOPE
様々な人たちと、社会に
HOPEを作り出していきます
EVENT
for HOPE
イベント開催情報や社会問題理解を
深める機会をお届けします。

ボーダレスで働く人、社会起業家についてわかるPODCASTを放送中

採用説明会やイベント、インターン
情報をいち早くお届けします!