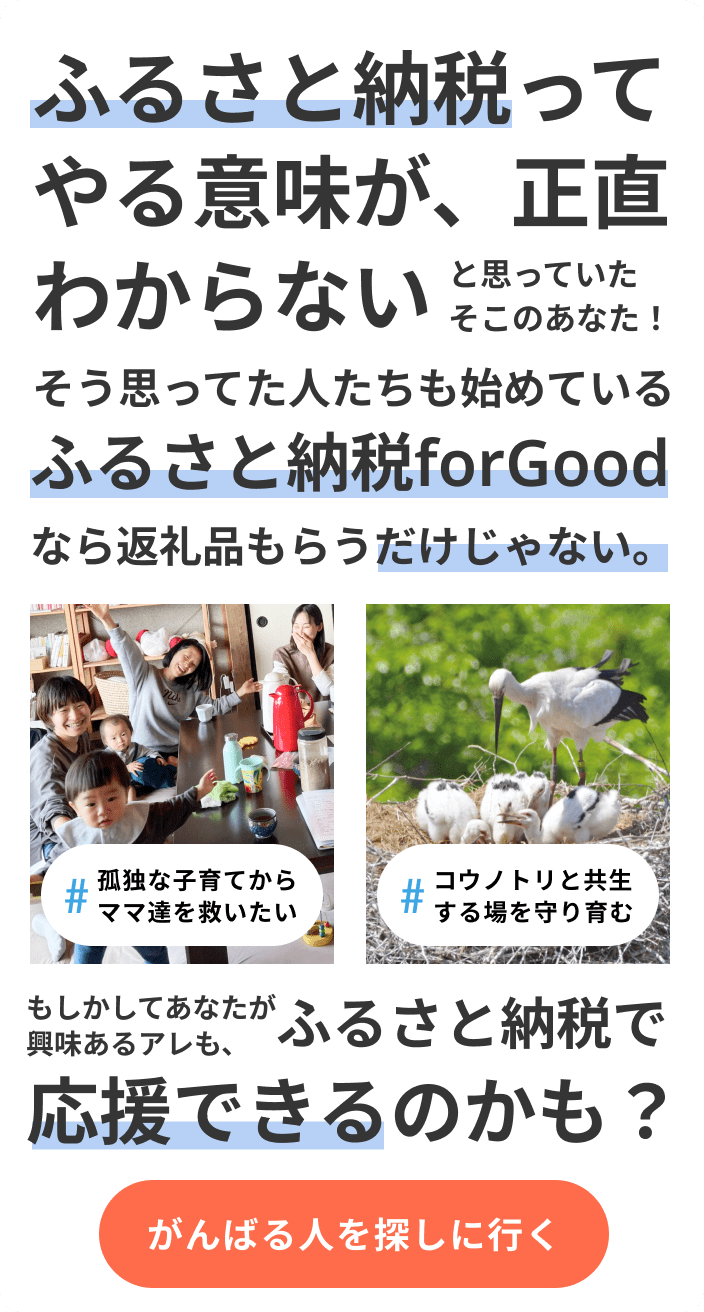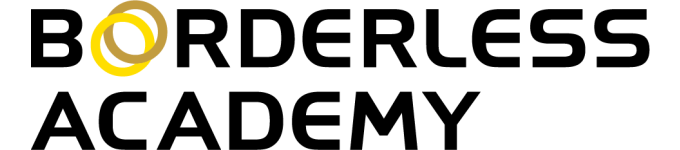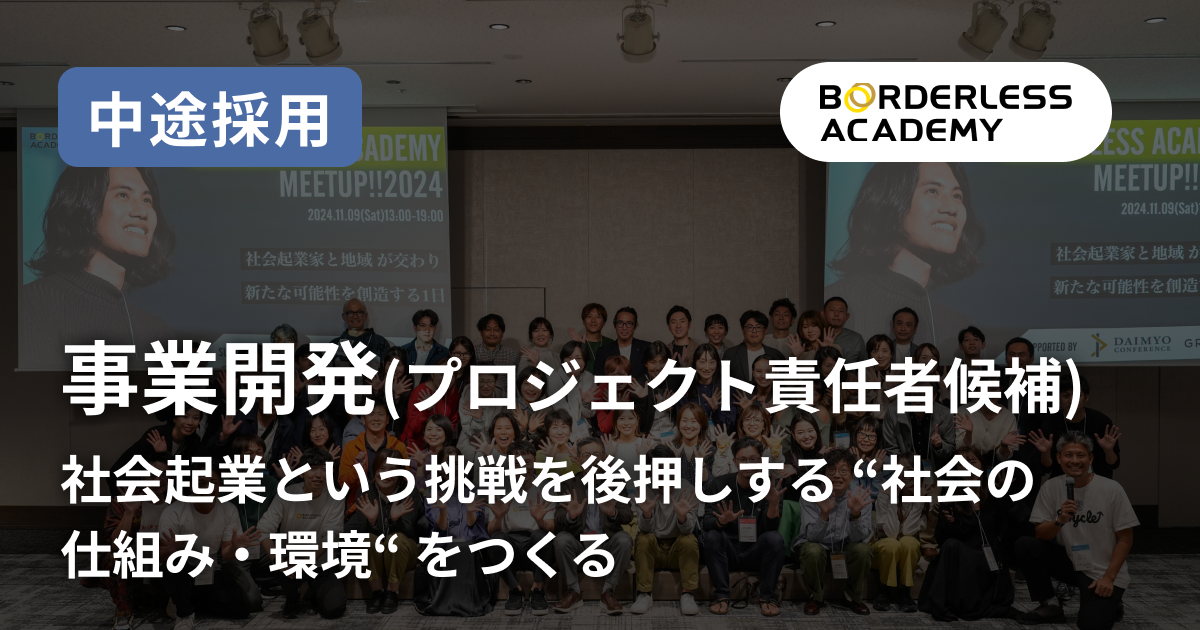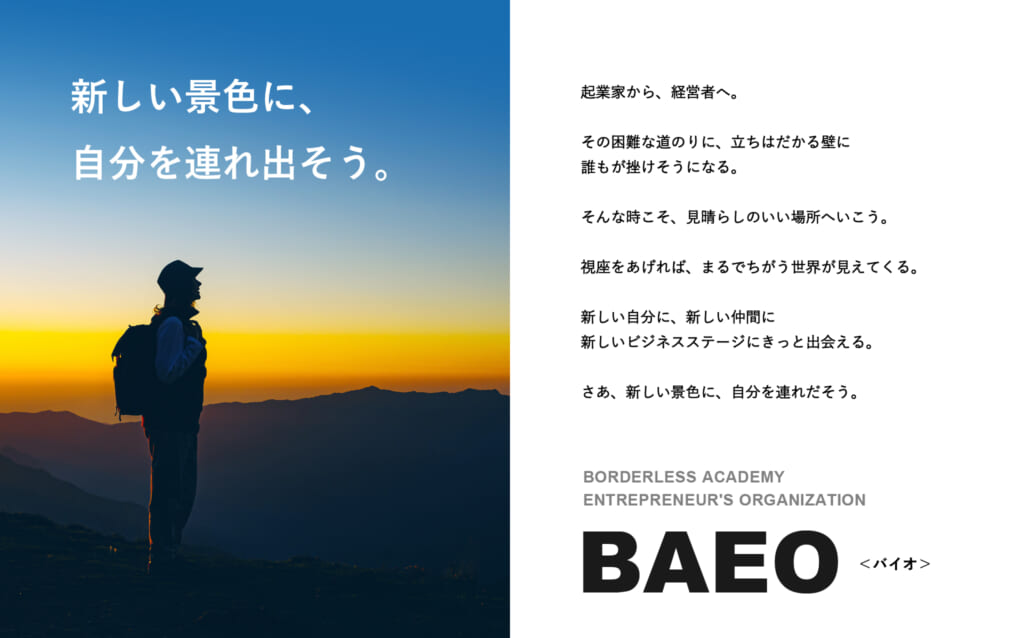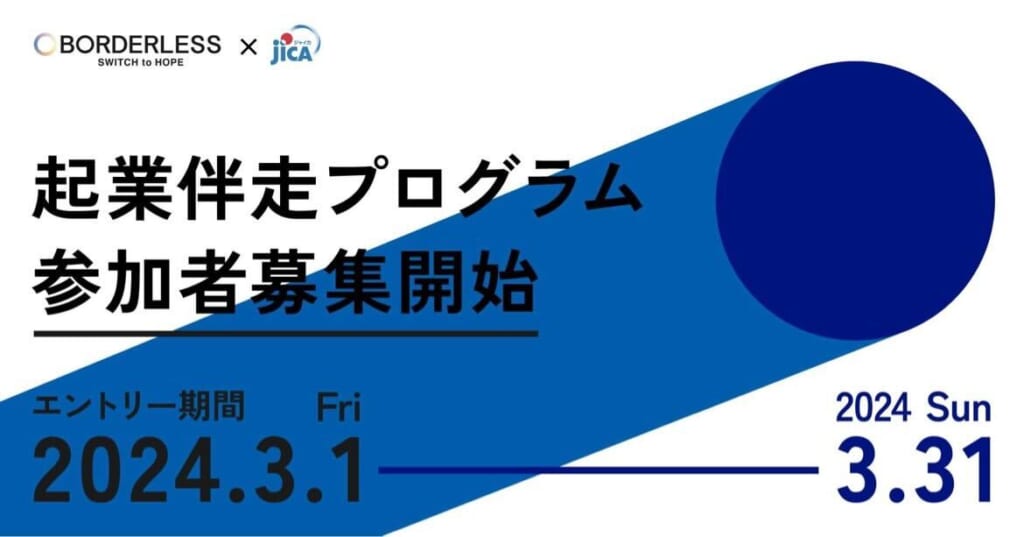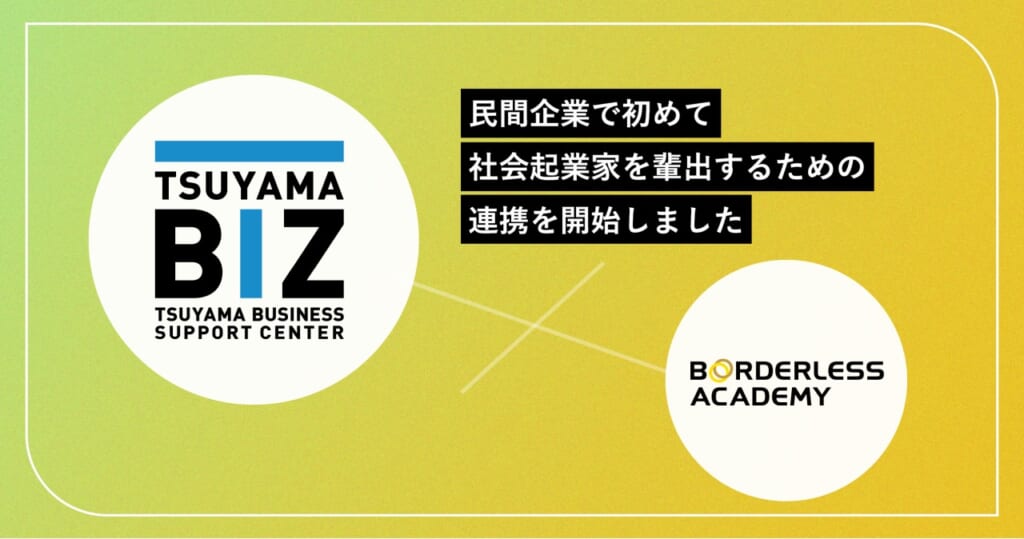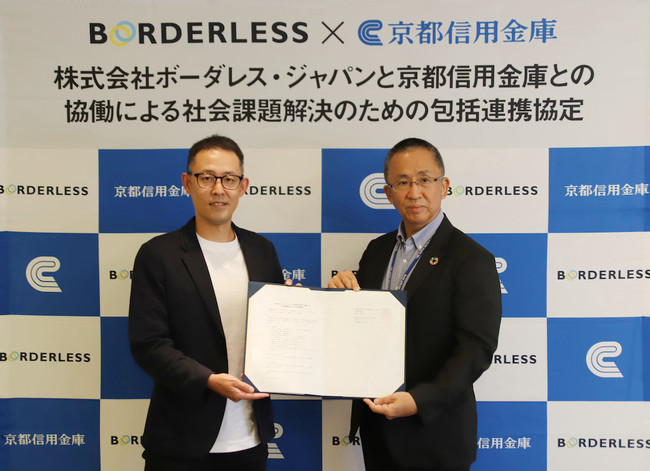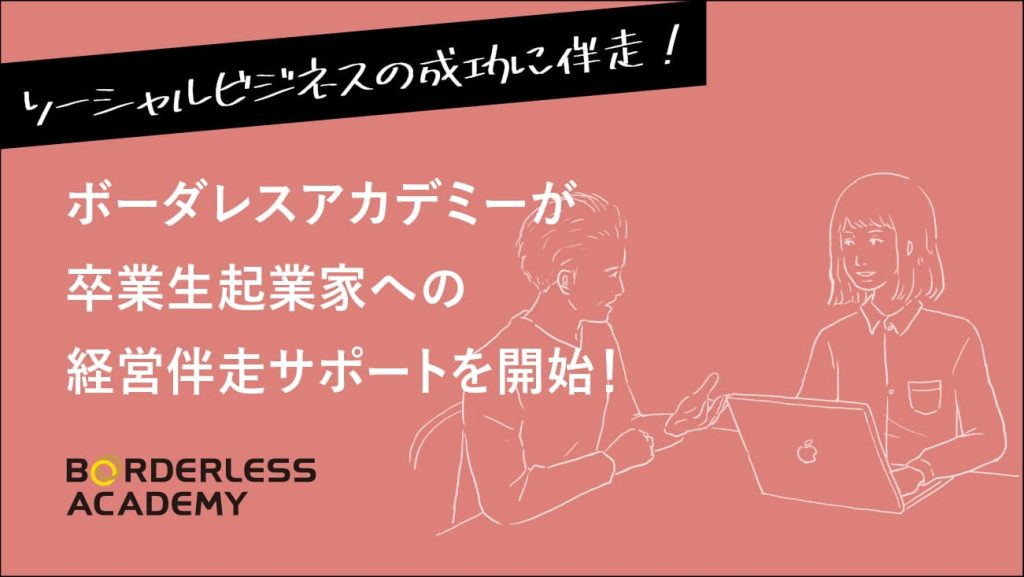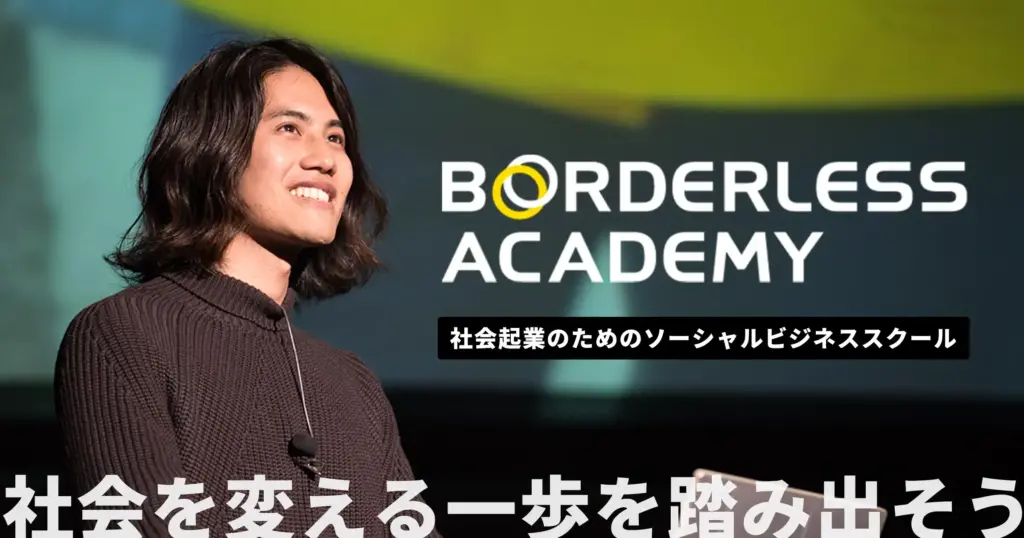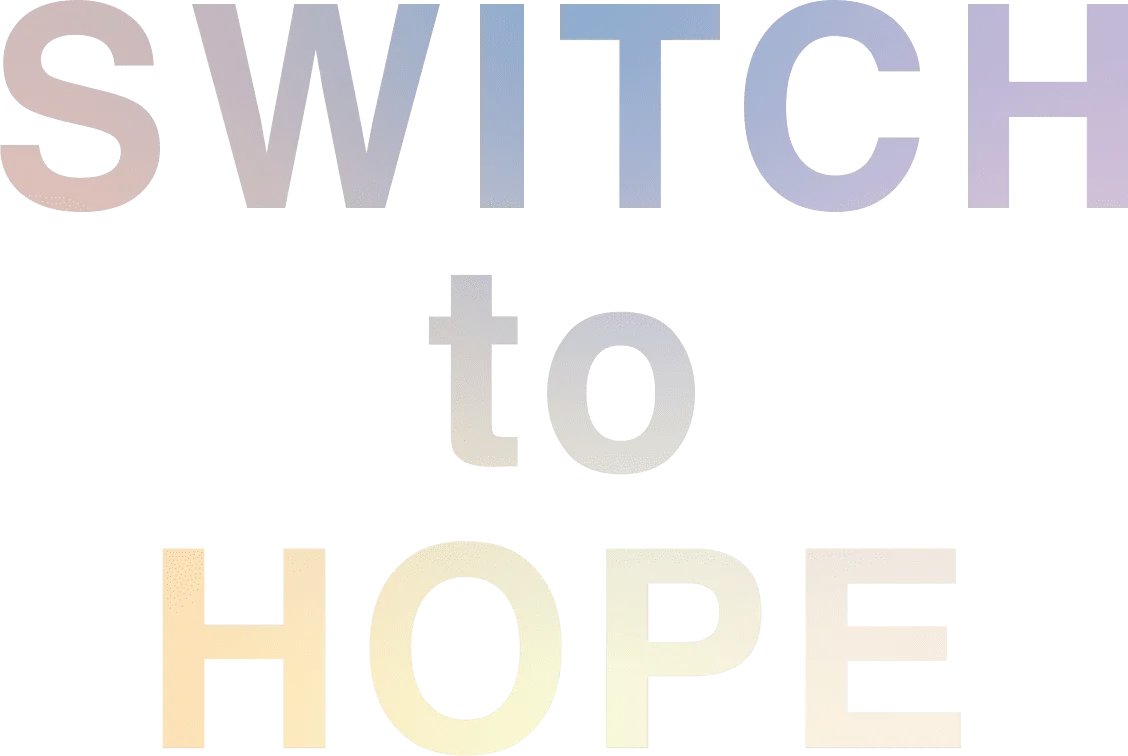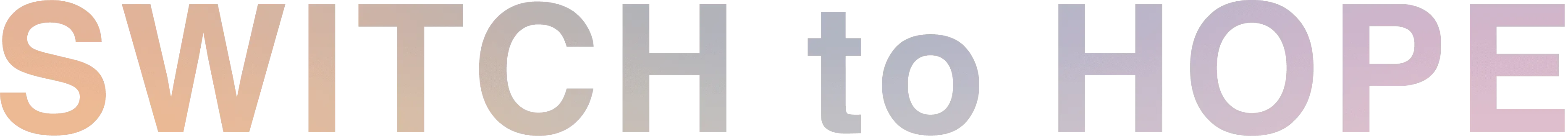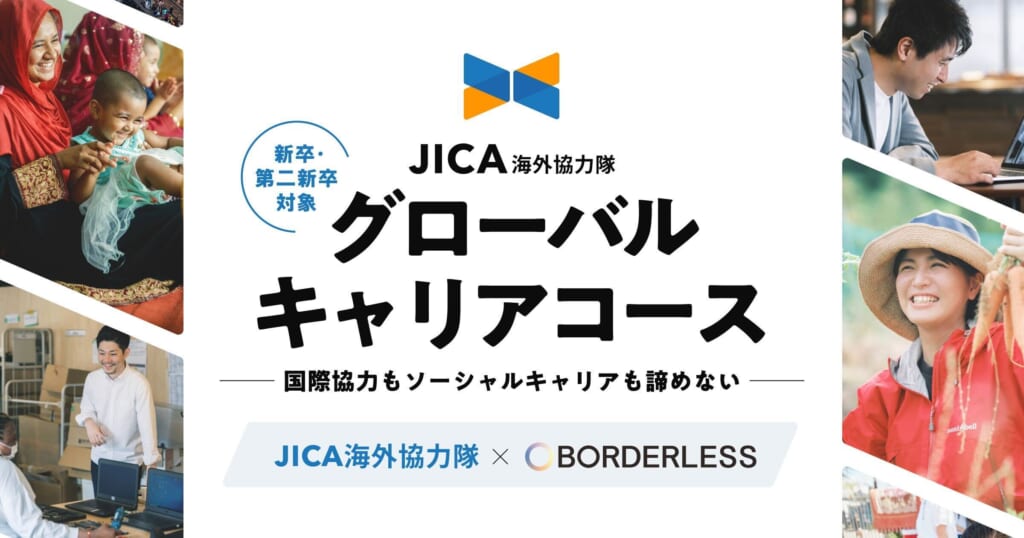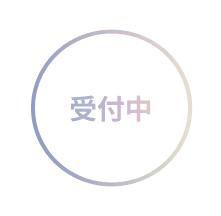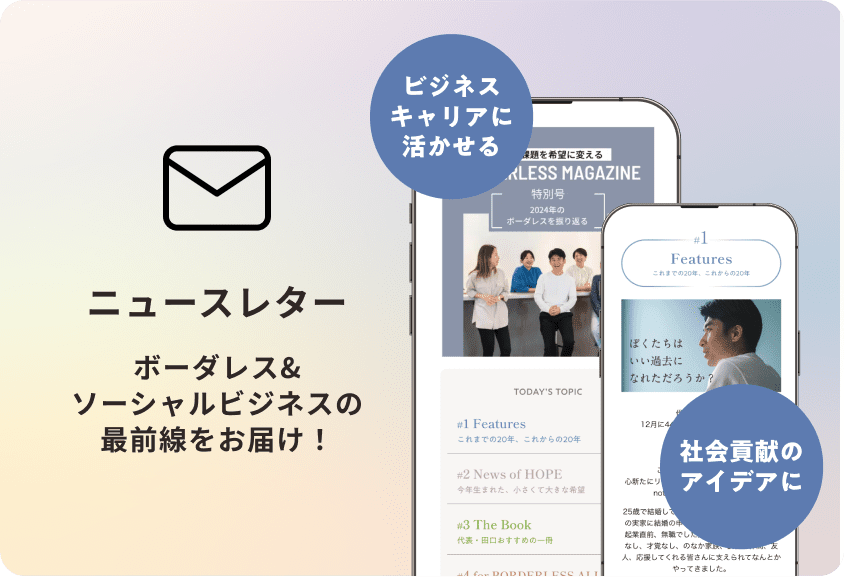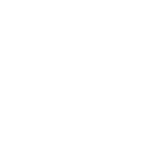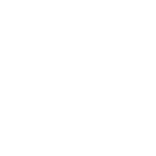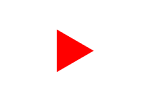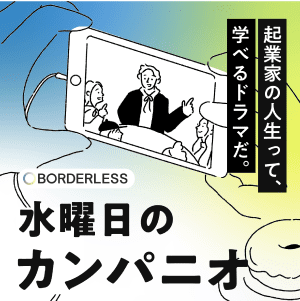NEWS
for HOPE
様々な人たちと、社会に
HOPEを作り出していきます
EVENT
for HOPE
イベント開催情報や社会問題理解を
深める機会をお届けします。

ボーダレスで働く人、社会起業家についてわかるPODCASTを放送中

採用説明会やイベント、インターン
情報をいち早くお届けします!