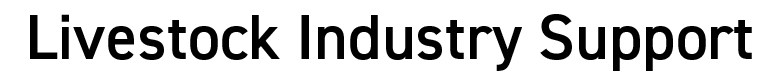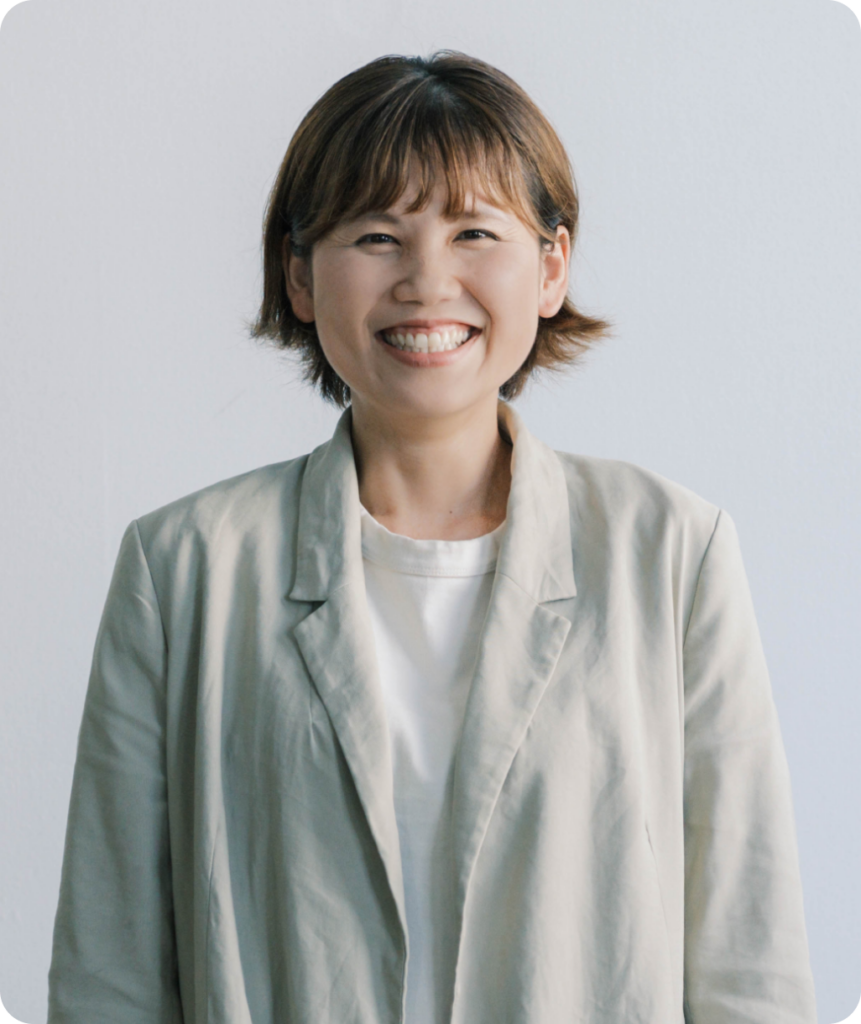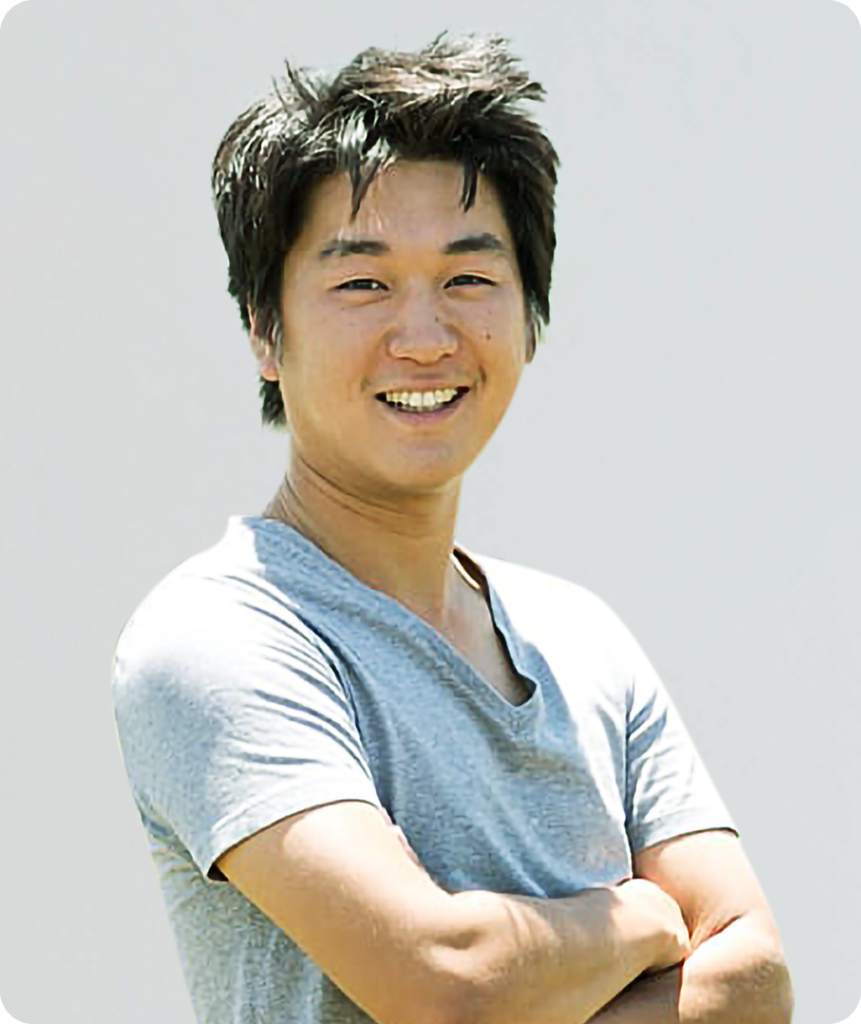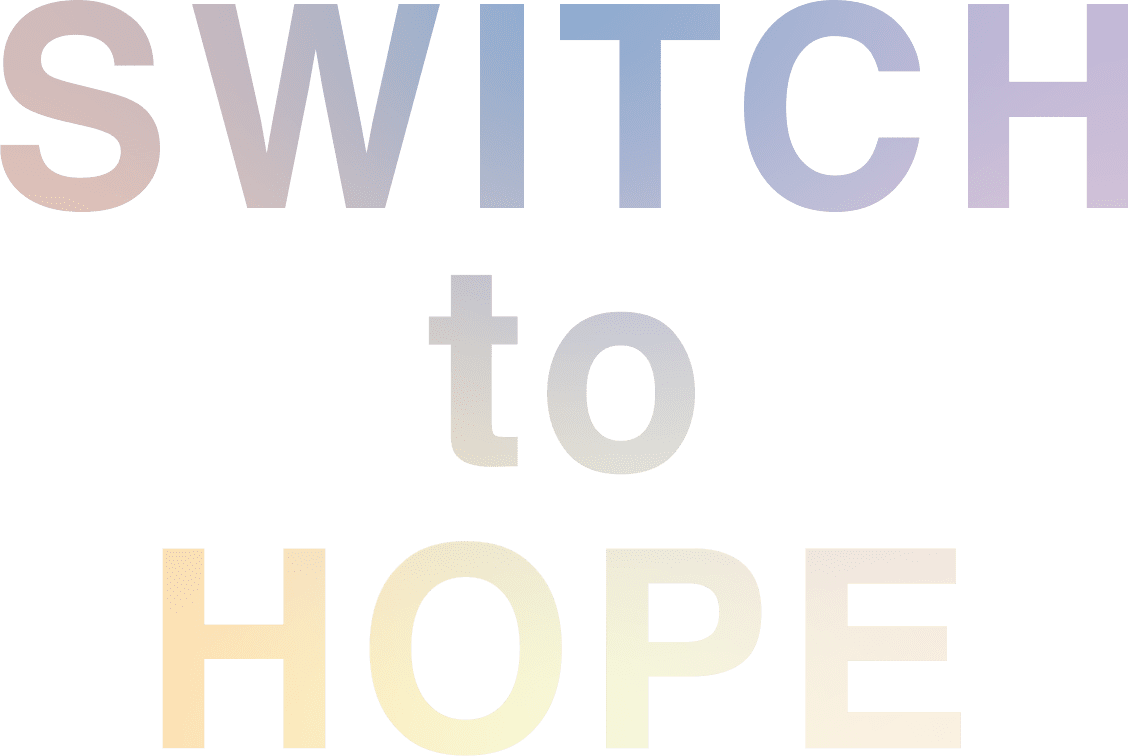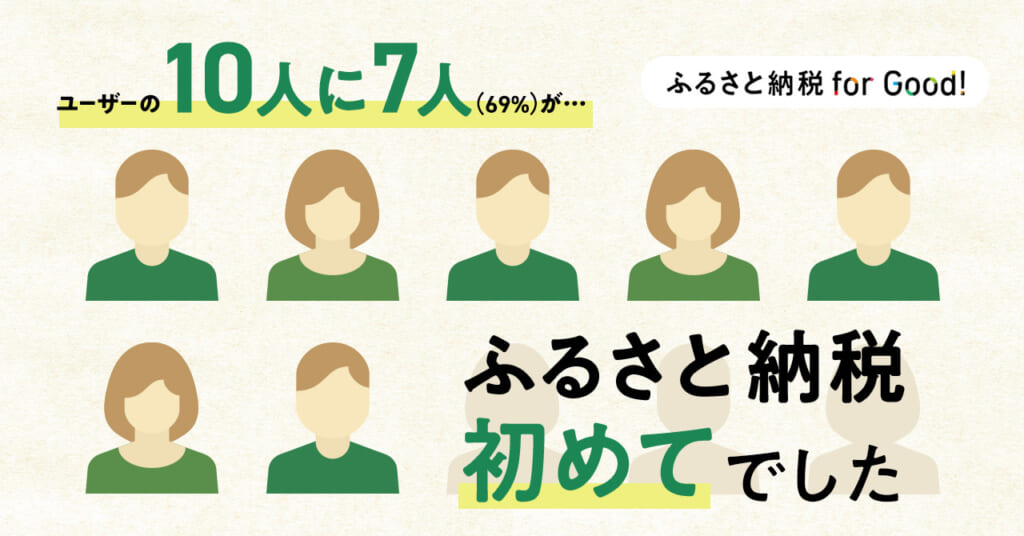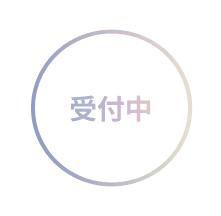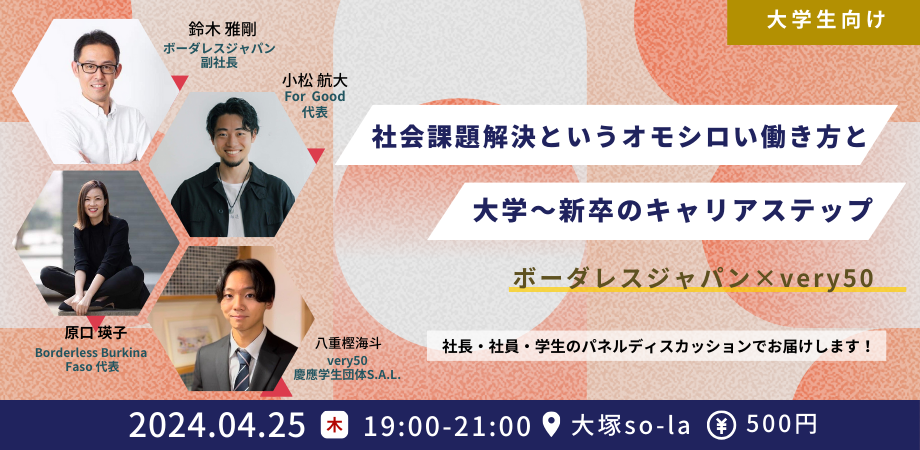MERI JAPAN 代表 柳下 智信

カンボジアの農村地域で、家計を支えるために幼い頃から働き出す子どもたち。大人になっても農業で得られる収入は低く、そのためまた子どもが働き出す。そんな貧困の負の連鎖を断ち切り、自分たちの意思で自分の人生を歩める社会を創りたい。
HISTORY
これまでの歩み
-
23才
株式会社ボーダレス・ジャパン 入社
ビジネスレザーファクトリーにて生産管理を担当
-
24才
POST&POST株式会社 入社
事業立ち上げ期に参画。店舗運営・店舗開発に従事
-
26才
みらい畑株式会社 入社
農業法人みらい畑にて事業開発に従事
-
36才
MERI JAPAN Co.,Ltd 創業
零細農家向けサービス事業をカンボジアで立ち上げ
01
どうしてボーダレスに?

新興国で一次産業に携わっている人は、勤勉な人が多いように感じます。勤勉に働いていても所得は不十分で、貧しい暮らしをしています。そんな頑張る彼らが報われてほしいと思い、小規模農家の所得向上に繋がるサービスを立ち上げました。
現状の社会構造では良い変化が望めない農村社会で、希望を持ってもらえるサービスを作りたいです。
02
今の仕事の喜びは?
農家の暮らしに如実に変化が現れたり、意識が変わったりする瞬間はとてもやりがいを感じますし、やっていてよかったなと思います。農業だけでは生計が立てられなかった農家が、養鶏を通して収入を得ることで、子供を学校へ通わす余裕ができたこと。また、そういった両親のチャレンジする姿を子供が見て、子供自身も新しく物事に取り組み始めたこと、など。好循環が生まれたときにやりがいを感じました。

03
次のチャレンジは?
農家がしっかりと稼げる仕事を提供できるJob maker になりたいと思っています。それは養鶏だけでなく、農家個々の家庭に合った仕事をという意味合いで考えています。
現在、養豚やカエル養殖などを小規模でスタートさせており、農業以外に農家が取り組める選択肢を増やせるプロフェッショナルを目指しています。そしてゆくゆくは農業分野でも農家にサービスを提供したいと思っています。

PROFILE
柳下 智信
1993年生まれ。北海道出身。日本大学卒。2016年ボーダレスジャパンに新卒入社。グループ内企業三社の事業開発を経験。2021年にMERI-JAPANを創業。学生時代に新興国で感じた「貧しいがゆえに選択肢のない状況」を打破したいと思い、小規模農家向けの養鶏委託事業を展開。農家の挑戦をサポートし、より良い暮らしを共に考える。特技はヴァイオリン。ラグビーは未経験。
わたしが働く会社
OTHER FELLOWS
他のフェロー
NEWS
for HOPE
様々な人たちと、社会に
HOPEを作り出していきます
EVENT
for HOPE
イベント開催情報や社会問題理解を
深める機会をお届けします。

採用説明会やイベント、インターン情報を
いち早くお届けします!